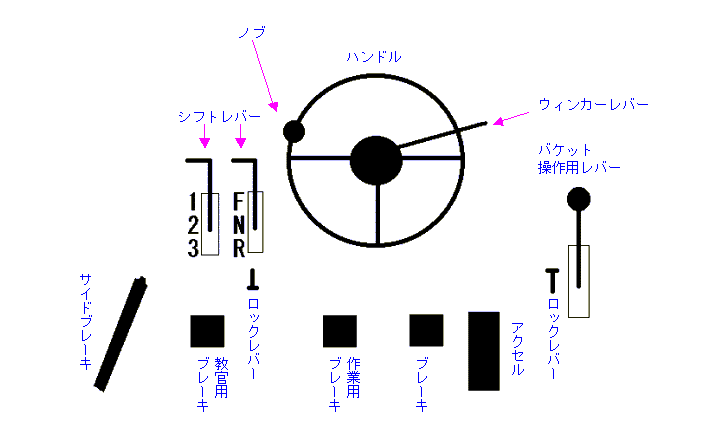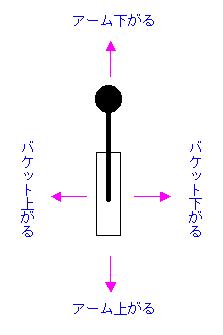大特教習記
 |
 |
| 教習所の教習車 |
鴻巣試験場の試験車 |
教習車は三菱製、試験車はコマツ製です。大きさも試験車の方が大きいようです。操作のし方も異なる場合があると思います。あらかじめご了承下さい。
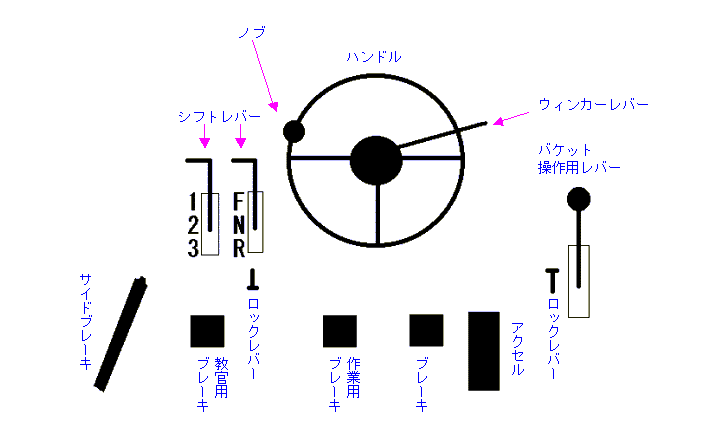 |
| 大特車の運転席の模式図 |
大特免許を公認教習所で取得する場合、最低6時間の技能教習が必要です。課題はきわめて少なく、大きなものは方向変換のみです。あとは踏切通過、見通しの悪い交差点、指示速度20km/hです。最短で4日間(1日2時間の教習×3日と検定)で卒業が可能です。
教習課程は3時限ずつ第一段階と第二段階に分かれます。第一段階では発進・停止、外周走行、右折、左折。第二段階で踏切通過と方向変換を練習します。
| 大特車の特殊性−発進・加速 大特車は作業車であるため、操作方法が他の車種とは違っています。運転席は上の図のようになっており、普通の車にはないバケット操作用レバーがついています。このバケットは駐車ブレーキの役割もあるため、停車時は地面に接地させておきます。ですから、発進するときはバケットを上げることから始めます。バケット操作用レバーは右の図のよう動かします。
まず乗り込んでシート調整、ミラー調整をしてシートベルトをします。バケット操作レバーとシフトレバーのロックを確認します。そして、ブレーキを踏んでエンジン始動、バケット操作レバーのロックレバーをはずし、初めに接地させているバケットをアームにつくまで上げます。それからアームを適当なところまで上げます(教習車にはテープで目印が付けられていました)。だいたいバケットの下端が地上から50cmぐらいになるあたりでしょう。アームを上げるとバケットとアームに再び隙間ができますので、さらにバケットを上げてアームにぴったりつけます。バケットの操作が終わったらまたレバーをロックしておきます。この間ブレーキはずっと踏んでおきます。
次にシフトレバーのロックをはずし、N(ニュートラル)からF(前進)に入れ、左側のレバーで2速を選択します。それから確認し、ウィンカーを出してサイドブレーキ解除、再び確認して発進します。
シフトはセミオートマチックなのでクラッチはありません。教官は「カブと同じ」と言っていました。シフトアップはややアクセルを戻して3速に入れます。
|
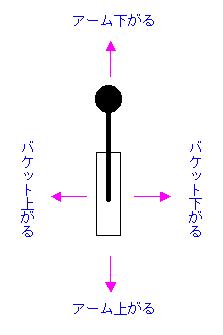 |
大特車の特殊性−停車時
発進時は運転席の右から左へ操作しました。停車時は逆に左から右へ操作することになります。まずサイドブレーキを引き、ギヤをニュートラルにしてロックします。そして、バケット操作レバーのロックをはずし、アームをバケット下端が地上10cmぐらいになるまでおろします。完全に下まで下ろさないのは、一気に接地させてしまうとバケットをおろせなくなるからです。バケット下端が地上10cmになったらバケットをおろし、バケット先端を接地させます。接地させたら操作レバーをロックします。それからブレーキを離し、シートベルトをはずしてシートを下げて降車します。
乗降時の注意
教習車の三菱はドアを一杯まで開くとロックされてしまいます。そうするとドアについている解除ボタンを押さないとドアを閉めることができません。これは一旦降りないと操作できません。乗車時はドアが全開にならないように注意が必要です。
中折れ式の特徴
埼玉県で使用される大特車両は中折れ式です。中折れ式は四輪すべてが操舵輪です。内輪差は発生しません。ですから、普通の車の感覚でハンドルを切ると大回りになってしまいます。左折の場合は前輪を縁石に沿わせれば、後輪は同じ軌跡をついてきます。右折の場合も「後輪がセンターラインを踏まないように」なんて考える必要はありません。前輪の位置をそのまま後輪が走るのです。
車体が折れ曲がるので、立て直しの感覚も少し違います。自分の位置で判断すると戻し遅れになりがちです。バケットのアームを目安にして、アームが進行方向まっすぐになるように誘導するとわかりやすいと思います。
ハンドルはノブを持って片手で操作するのが基本です。もう一方の手は補助的に添えます。「持ちやすい方の手で持てばいい」と言われましたが、私は左手を主体にしました。シフトの頻度よりウィンカーを操作する頻度の方が高かったからです。
ところで、図ではノブの位置が左側にきていますが、この位置は一定していません。走っているうちに動いてきます。これも中折れ式の特徴なのだそうです。ですから右側にノブがきているときは右手で操作した方がやりやすいかもしれません。
なお、ウィンカーはオートキャンセルになっていません。進路変更、右左折が終わったら手動で戻さなければなりません。でも、逆に考えると、カーブで合図が戻ってしまい、出し直すのを忘れた、というようなミスは絶対ありません。
課題でバックを要するのは方向変換のみです。バックの場合も後向きに前進しているという感覚で大丈夫です。普通の車のように気持を切り替えるとかえってマイナスです。内輪差がない、前輪も後輪も同じ動きをする、ということを肝に銘じておきましょう。
本来走行することが目的の車両ではないので、直進性はきわめて低いです。おそらくホイールアライメントなどというものもなく、ただ車輪がついているのでしょう。直進時に気を抜くとふらついてしまいます。教官も「大特は直進時のふらつきを一番見ている」と言っていました。
ギヤの選択
シフト操作については前述の通りです。F−R切り替えレバーと1〜3速選択レバーを間違えないように注意が必要です。シフトアップのつもりでF−R切り替えレバーを操作してしまうとバックに入ってしまうことがあります。それ以外は、セミオートマチックということもあり、難しいことはありません。
ギヤは発進時は2速、10km/hぐらいで3速にシフトアップします。あとはほとんど3速のままでOKです。カーブも3速のままで抜けられます。概ね10km/hを目安にギヤを選択すればいいと思います。教習中2速を使ったのは、左折、見通しの悪い交差点、一時停止後などです。
なお、方向変換のときはRをセレクトした上で1速を使いました。
踏切の通過
教習車の三菱車は運転席の窓がはめ殺しでした。教官に「踏切の窓あけはどうしたらいいのですか?」と聞いたところ、「大特はやらなくていいです」という答えでした。もちろん、一時停止、左右確認、通過するまでギヤチェンジしないということは他と同様に実施します。
鴻巣の試験車両について
免許センターで大特一種及び二種を取得されたさむさんから、試験車両の詳細を教えていただきました。まず、試験車両は窓が開くとのことです。窓が遠くて、乗車後に開けるのは難しいため、通常は乗車時にあらかじめ開けておくそうです。
また、シフトレバーはハンドルコラムについているようです。そして、発進は1速で行うようです。
戻る
|